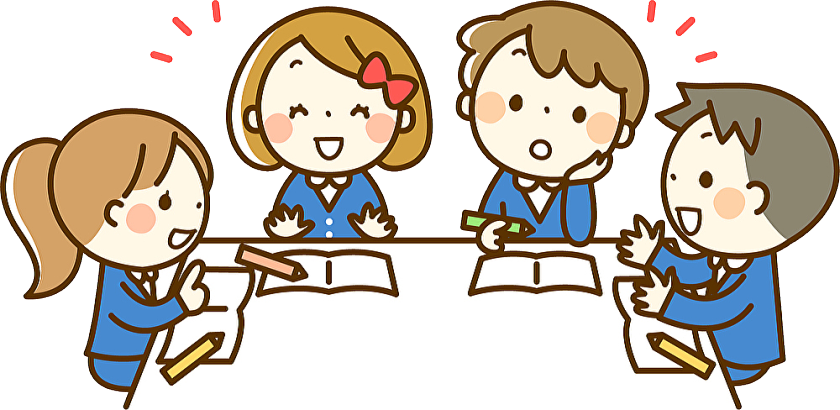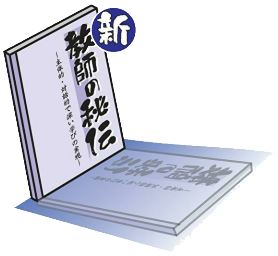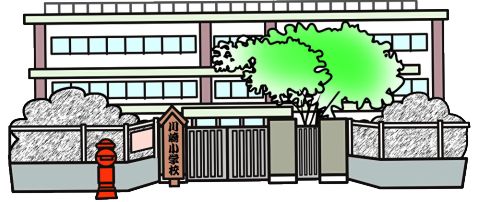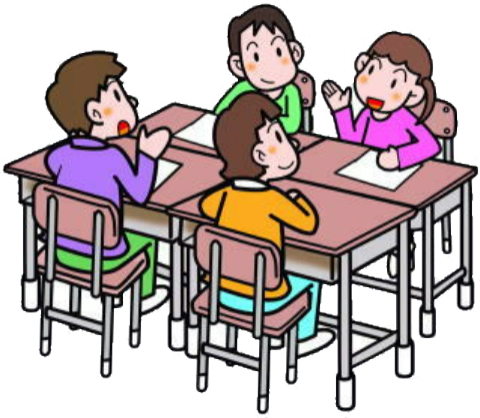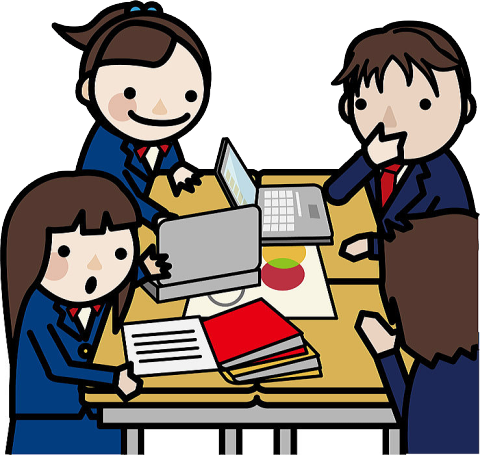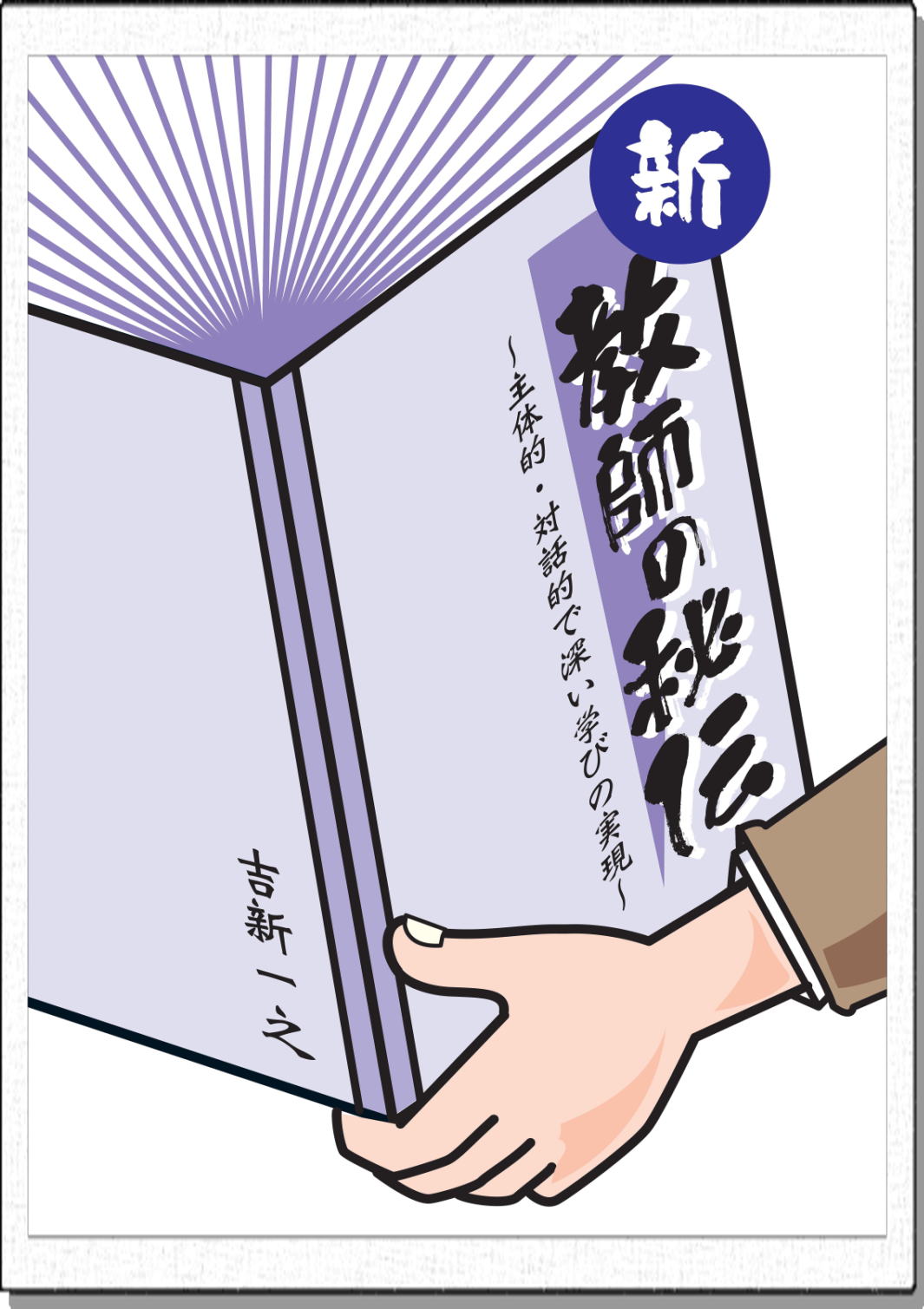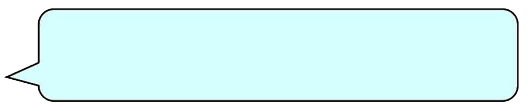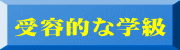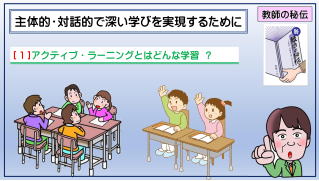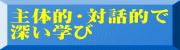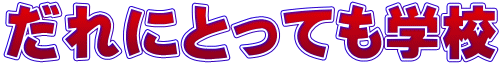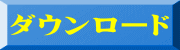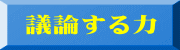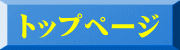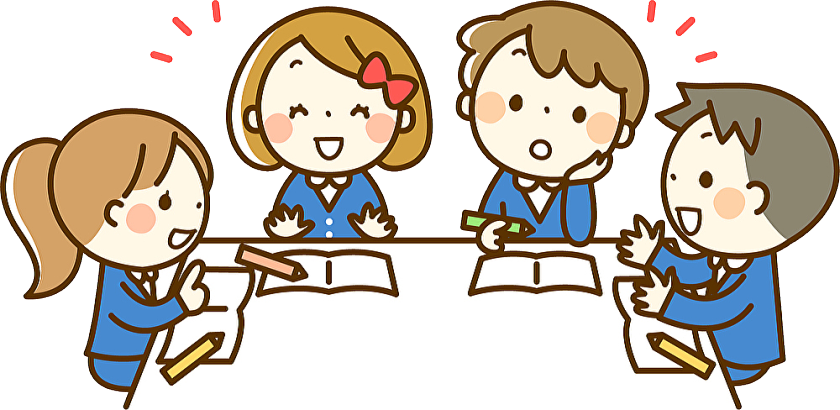 |
「主体的・対話的で深い学び」の学習過程は、学習問題を設定して、一人一人が解決のための考えを持って、みんなで話し合い、「最適解」と言われる共通の考えを作り上げたり、解決のための「新たな考え」を創造したりするものです。この過程を通して、子ども達一人一人に「資質・能力」が養われます。 |
 |
そのためには、一人一人が「多様な考えを出し合う」ための「考えを広げる話し合い」と「問題解決」のための「考えをまとめる話し合い」が大切です。この話し合いは、「議論」のことです。「少数意見」を取り入れながら、みんなで「問題解決」のための考えを作り上げていくことが大切です。 |
 |
「主体的・対話的で深い学び」を実践することで、「議論する力」をつける教育が実現すれば、一人一人にとって「よりよい社会」を実現することにもつながります。 |
kzyk.y8025@gmail.com
Copyright ©2016 kyoushinohiden All Rights Reserved.
よしあら かずゆき
教育力向上アドバイザー
このような学びの場が確立されると、学校を「自分の居場所」と感じる子どもが増えます。その結果、不登校の大きな要因の「疎外感」や「学びへの不安」が軽減され、「学校がより安心できる場所」となることで、「不登校の減少」にもつながります。
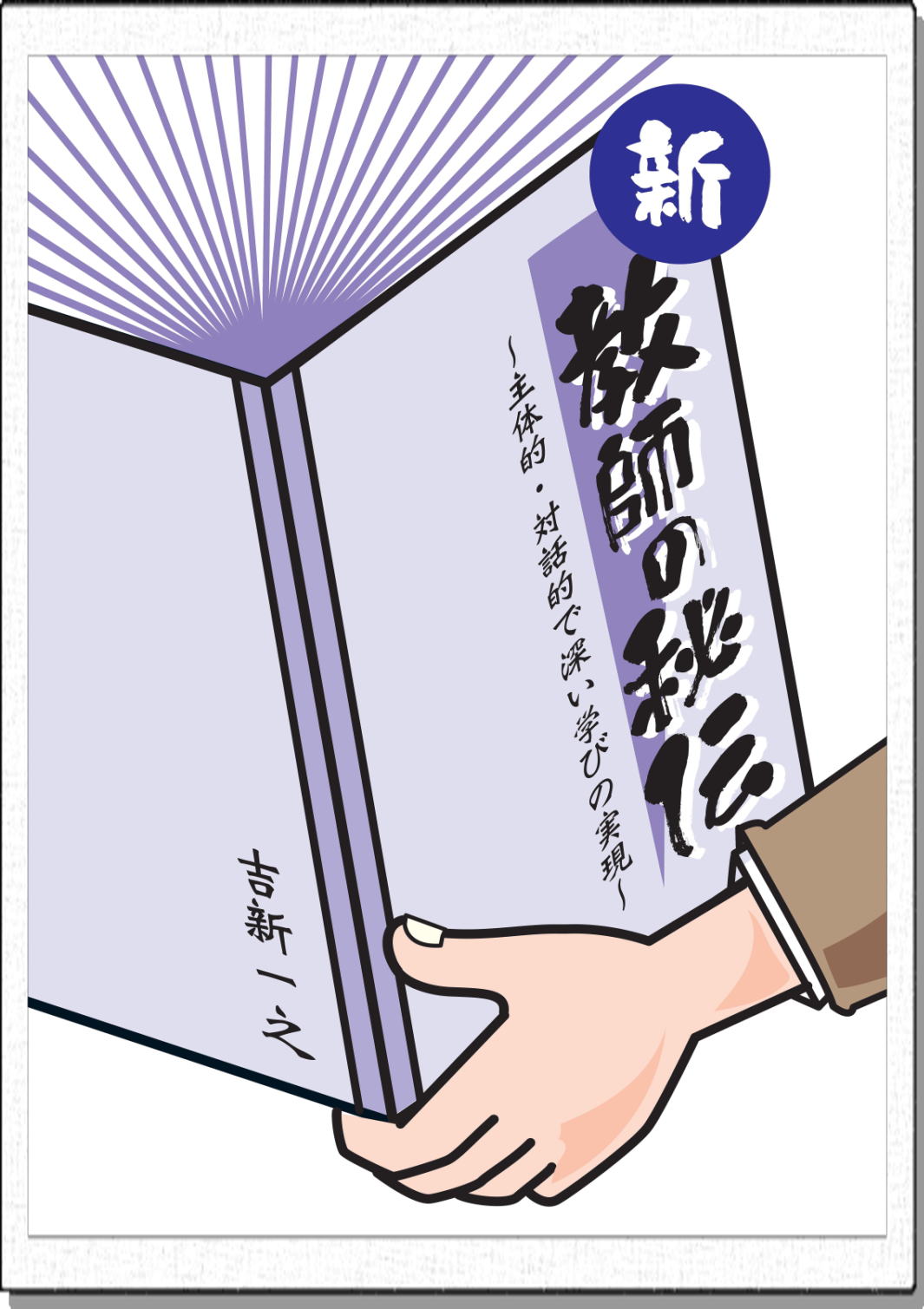 |
左の「教師の秘伝」をクリックすると、目次が見られます。
「ダウンロード」のページからPDFでダウンロードできます。 |
| これからの時代をよりよく生きるために最も必要な「資質・能力」は、人と「議論」して、「最適解」を作り上げたり、「新たな考え」を創造したりして、人と「協働」して「問題解決」する力です。 このような「資質・能力」を育成するために、「主体的・対話的で深い学び」を実現することが求められます。
|
従来の授業では、教師主導のもと、児童生徒が決められた答えを発言する受け身の学習が一般的でした。しかし、「主体的・対話的で深い学び」では、子どもたちが自由に意見を出し合いながら問題を解決し、自分の考えが尊重されていると感じられるようになります。
また、他者との対話を通じて深く考えることで、思考力の向上につながります。さらに、意見を尊重されながら周囲と協力して学ぶ経験を積むことで自己肯定感も高まります。
どの子でも受け入れられ、一人一人に「居場所」がある「受容的な学級」では、一人一人の個性や能力に応じた力を発揮することができるようになります。このような「受容的な学級」が「主体的・対話的で深い学び」の成立要件となり、「いじめ」や「不登校」、「学力格差」の問題解決につながります。
ご質問等ありましたら、下記アドレスにメールでお知らせください。
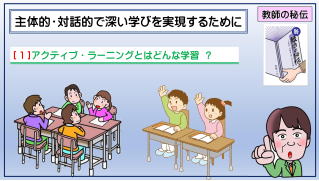 |
「動画説明」のページにリンクします。左の図をクリックしてください。 |
すべての子どもが安心して通える学校を実現するには、「どの子も受け入れられ、居場所がある」と感じられる環境が必要です。そのための重要な取り組みの一つが、「授業のあり方の見直し」です。
特に「主体的・対話的で深い学び」を重視することで、より良い教育環境を整えることができます。
「主体的・対話的で深い学び」を重視した授業改善は、すべての子どもが受け入れられ、「どの子も安心して学べる学校づくり」に直結します。これを実現することが、不登校を生まない学校、つまり子ども一人ひとりの違いを尊重し、それぞれの可能性を伸ばすことができる学校づくりのための大きな一歩となるのです。
このような学びの実践により、教師は子どもたちの考え方や個性・興味・関心を深く理解できるようになり、それぞれに合った支援が可能になります。その結果、学校全体の教育活動が改善されます。
さらに、「学校生活の中で最も長い時間を占める授業」が変わることで、児童生徒の成長に大きな影響を与えます。
加えて、「授業」だけでなく、「学校行事などの集団活動」においても、「見た目の完成度」や「勝ち負け」だけでなく、一人ひとりの関わり方や成長の過程に注目し、行事の在り方を見直すことが可能になります。